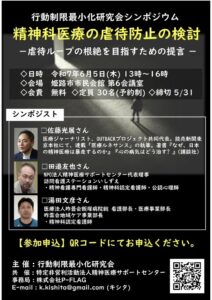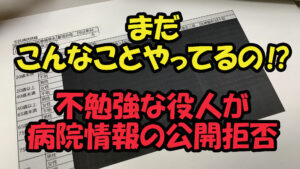佐藤光展の「精神医療ルネッサンス」日精協会長・山崎學さんの「〝悪役〟の胸の内」/国が「保安」をやらないから民間が/感染症対策は独自ネットワーク検討(2021年9月の記事の再掲載)
2021年7月31日、NHKが放送したETV特集「ドキュメント 精神科病院×新型コロナ」の中で、日本精神科病院協会の会長・山崎學さんがふと漏らした言葉が波紋を広げました。
「精神科医療というのはね、僕はよく言うんですけど、医療を提供しているだけじゃなくて、社会の秩序を担保しているんですよ。街で暴れている人とか、そういう人を全部ちゃんと引き受けているので。医療と社会秩序を両方精神科医療に任せておいて、この(診療報酬)点数なんですかって言っているわけ。一般医療は、だって医療するだけじゃないですか。こっちは保安までも全部やっているわけでしょう、精神科医療って。(入院を)断っていたらどこもとらないし、一番困るのは警察だと思うよ。警察と保健所が困るだけだよね」
この発言に対して、方々から非難の声が上がりました。日本の民間精神科病院を束ねる組織のトップが、医療だけでなく「日本の保安も担っている」と明言したのですから、それは衝撃的です。しかし、私は困惑や怒りよりも、「よくぞ本当のことを言ってくれました」と、山崎さんに拍手を送りたい気分でした。私たちが見て見ぬふりをし続けた「医療という名の保安処分」の存在を、関係組織の親分が自ら認めたのですから。8月19日、東京・芝浦の日精協会館で、山崎さんに会ってきました。3時間近くも話を聞かせてくれました。
まずは、ETV特集の感想と保安発言の真意から(★の後のカギカッコは当時の副会長・野木渡さんの発言)。
「NHKのあの番組は、(東京都立)松沢病院でコロナの病棟を運営していて、コロナ下の精神医療がどうなっているか、というのがテーマなんですよ。僕は3時間くらい取材を受けたけど、断片的な部分だけが切り取られてしまった。まったく関係ないところだけをポンと出しちゃっているので、誤解を生むような放送の仕方をしちゃっている。あれはNHKの編集能力の問題、あるいは恣意的に物議をかもそうと思って、あそこだけを切り取って出したのかね。編集者にも『これはおかしいんじゃないか』ということは言ったんだけどね」
「僕が言ったこと自体は、間違っているとは思っていないんです。措置入院にしても、スーパー救急にしても、今どうにかして欲しい患者さんを、家族や警察、保健所が言ってきて、精神保健福祉法に基づいて強制入院をさせる、というシステムでやっているわけですよ。例えば、心筋梗塞で病院に運ばれるのとは違うと思うんだよね。そこで暴れている人は、どうにかしなきゃいけないわけで、そういう患者さんをきちんと法に則って入院させる。そういう手続きをして、更に、興奮状態に対して医療的な提供をしているわけじゃないですか。そういう2つのことをしているのに、危機的状況においての(診療報酬上の)評価が全然ないというのはおかしいと、僕は前から言っているわけ」
「あと思うのは、左の人達は、精神科医療について斜めの姿勢で見る癖がついちゃっているからね。国家権力に与してやっている、精神病院は敵だ、みたいな煽り方が一方ではあると思いますよ。ただこちらは、法律にのっとってやっている話であって、老人病院で暴れる患者さんを(違法に)拘束するのとはわけが違うんだからね。そこらへんを、一般の人は全く分かってないと思うんだよね。精神科医療での拘束は、精神保健指定医が診察して、カルテに書いて頻繁に観察して、という手続きを踏んでいるわけじゃないですか。老人病院の場合は、誰が判断しているのかもわからない。老人病院などで拘束ゼロ運動なんてやっているけど、拘束しているよ、実際は」
1950年代以降、国の隔離収容政策の下で乱造された民間精神科病院は、生まれながらにして「保安」機能を担わされてきました。狭量な国民や行政が「面倒」「目障り」「邪魔」「危険」と考える人々に対して、精神科医が適当な診断名を付けて、収容を続けてきた歴史があります。ただ、民間精神科病院のトップの口から「保安」という言葉がダイレクトに飛び出すと、衝撃を受ける人は多くいます。
「(保安という言葉以外の)適切な言い方が分からないよね。柔らかく言うとまわりくどくなるし、やっぱり社会秩序の担保だと思うよ。例えば、包丁を振り回している患者さんなんて、そのまま放っとけないじゃないですか。警察が取り押さえて、ある程度拘束して、そのまま病院に連れて来て診察して、精神疾患による急性錯乱ですね、ということで医療的な治療に入るわけじゃないですか。でも、法に則って拘束して治療した、というところの評価ってないじゃない。心筋梗塞なら、その人だけの問題だけれども、精神科病院っていうのはその患者さんだけの問題じゃなく、周辺にいる人達へのリスクも背負って収容しているわけです。そこの部分について、なぜ評価しないのか僕はおかしいと思っている」
「一般の人にとって、精神科の問題は特殊であって、身内にそういう問題が起きなければ所詮は他人事なんですよ。認知症でも同じだと思うよ。身内に認知症患者が出ちゃって、夜間徘徊したり、衝動行為でいろんなものを壊したりだとか、そういう風になって初めて、これは大変な病気だって理解ができるんだけども。身内に統合失調症の患者さんがいなければ、そんな考えにならないよね。発達障害もそうだし、双極性障害にしてもそうだし、やっぱり他人事なんだよね」
「精神科の医療機関が勝手に暴走しないように、精神保健福祉法というタガがかかっているんですよ。昔の精神病院法から始まって、その頃というのは行政自体もずっとおかしなことをやっていたわけで。精神科医療って外国みたいに国がやるべきなんだよね。公的病院できちんと担保して、民間病院を1割くらいにすべきなのに、日本は低医療費政策で精神医療を安い値段でずっとやってきて、病床ばっかりつくっちゃって、地域にある中間施設の整備をしなかったわけじゃない。そこに問題があるんだよね」
「日本の精神科医療っていうのは、民間の病院を代用として使うという、そもそも始まりからして問題があると思うのよね。1919年に精神病院法という法律ができて、本来ならば政策医療でやるべき部分の精神科医療までも、代用の精神病院という考え方を導入して、民間病院に全部投げちゃったんだね。そこのところに大きな問題があったんじゃないかな」
「それともう一つ、(精神科病院の問題を語る時に)報徳会宇都宮病院の話がよく出ますよね。この事件は世界的にも有名なんだけど、この問題の根本には、処遇困難な患者を全部、民間病院に振ったという所にあったと思うんですよ。昭和44年(1969年)に大阪で安田病院事件というのがあって、不審死がたくさん出るんだけど、近畿一円から処遇困難な患者を全部ここに送っていた。この事件があった時に、大阪府立中宮病院の事件とか他にも色々あったのに、この時にきちんと総括しておかなかったのがいけない。処遇困難な患者は公立病院で診るのが普通でしょ。安田病院に全部送っていた行政が悪い。もちろん事件を起こした人も悪いんだけどね」
「そして、安田病院は大和川病院と名前を変えるんだよね。変えてまた、たくさんの不審死が出て、結局、廃院になったんだけど、厚労省の高官が関係していたんだよね。病院の貴賓室で接待を受けていたみたいで。よくある話。そして、安田病院事件から15年経ってから、宇都宮病院事件が起きる。この病院のモデルって安田病院だったんだよ。安田病院事件の時に、きちんと行政が介入して、処遇困難例を民間に押し付けるのはやっぱり変だろうという話でやっておけば、防げたかもしれないのに。僕の地元の群馬県の処遇困難例は、みんなここに送っていたんだよ。人格障害に精神障害が嚙んでいるみたいな人は、どうにもならなくてね」
「法務省が昭和49年(1974年)に、刑法を改正して保安処分というのを提案した。ところが当時、日本精神神経学会がみんな左の全共闘だったんで、これを潰しちゃうんですよ。彼らはそのまま被害的になるものだから、こんなものができて反政府運動をやったら、みんな保安施設に入れられてしまうんじゃないか、という被害妄想みたいなのがあって、潰しちゃって。結局、池田小学校事件が起きるまで、これに類する法律が作れなくなっちゃって、池田小学校事件であれだけの犠牲を払ってやっと医療観察法を作るわけ。ところがこれがザル法案もいいところで、治療可能性のある患者しか対象としていないんだよ」
「治療が極めて厳しそうな患者さんは、精神科病院に措置入院で入ってくるんですよ。医療観察法の入院費はひと月に180万から200万ぐらいでしょ。措置入院で入ってくる患者さんは70万か80万ですよ。半分くらいで、もっと重症な患者さんを措置で民間に押し付けているっていうね、全然合わないわけ。医療観察法の場合、まず精神科病院で鑑定入院というのをやるんですよ。鑑定入院した時に治療しちゃうからね。(公的な医療観察法病棟に)1年半の入院処分になって、入る時には半分くらいは良くなっているんだよ。だから別段、医療観察法にする必要はないんだ。だって良くなっているんだもん。それにひと月200万ぐらい払ってる」
★「僕の考えから言うと、日精協の中にも基本的には精神科は治療する場所であって、保安処分を取る場所ではないという会員は過去にたくさんいたし、今もいると思います。基本的には、そういうことは公的病院がするべきだと。根本的な姿勢であったと思います。ただ会員の中には、医療と保護という部分で、患者さんを保護するという意味合いの部分では、精神科が担っている部分もあるというところで、ある意味、保安的なところにつながっているという考えもあります。保護という部分無しには、精神科で治療はできないというところです。しかし、保安処分を精神科が受けるのはおかしいという議論はずっとあったと思います」
★「だから、措置入院の患者さんを取らない病院は結構ありましたよ。それで国が困って、スーパー救急に措置入院をどれだけ取っているのかというのを施設基準に入れるわけですよ。取らざるを得なくしたわけですよね。すると、我々もせずには病棟を維持できませんから。患者さんも減ってきている中で、どういう風な生き延び方を考えていくのかという形になってきた所で、措置入院を考えざるを得ない状況になってきたのかなと思っていますね」
「日精協の存在意義というのは、公立病院の下請けじゃないんだよ。町工場じゃないんだから、精神科医療の最先端のところをきちんと、自らやっていかないとさ、我々は公立病院の下請けになっちゃうから。率先して日精協が音頭をとって、今みたいにやっていかなきゃダメなんだよ」
NHKの番組の中で、山崎さんが言った「街で暴れている人」という言葉も、「精神科患者への差別を助長する」などの批判を浴びました。こうした声を、山崎さんはどう受け止めたのでしょうか。
「(街中で暴れる精神疾患の患者は)いるよ。発症している時は、暴れる人もいるよ、それは。暴れているから(警察などに)連れて来られるんであってさ」
★「患者さんが悪いわけではないですよ。病気だからですよ。薬を飲めば落ち着きます」
「病院に収容されるまでは、周りの人に何をするか分からないじゃない。こっちも斬りつけられるか分からない患者さんを治療しに行くわけだから。しかも、法的手続きでは、あなたはこういう病気だからって、支離滅裂な患者さんに告知するんだよ。法律屋が作ったバカな法律だよね。分からない患者に病状を説明しろってさ。こういう大変な保護の部分が精神科は保障されていないんだよ。だから、ちゃんと(対価が)払われるべきだと」
★「そしたら、人を増やせますからね」
「本来なら、すべて公立がすべきだと思うけど、公立がやらないんだもん。やらないから結局、日精協がやるしかないんだよ。他でやるとしたら、どういう所を想定しますか。想定なんてないですよ。少なくとも病気なんだから、医療が絡まなきゃダメでしょ。一般の先生がやってくれるかといったら、とても精神科なんて分からないって言うだけだよ。精神科医療でやるしかないし、保健所なんかもあてになんないよ」
★「昔は、警察が暴れている人を見ると、本当にすぐ精神科病院に連れて来ていましたよ。それが酔っぱらって暴れている人でも。最近は、酔っ払いは一晩醒ましてから来てくれって。昔は、わけがわからないことで暴れている人は、全部精神科に連れて来られましたよ。興奮している方の中には、やっぱり精神疾患の方がいるので、我々が診察して、措置入院や治療にのせると」
「あと、最近よく家族や保健所が連絡してくるのが、過量服薬とリストカットね。外科とか整形で縫合してからね。過量服薬は向精神薬もあるし、市販の薬を大量に飲んだというのもある。自殺したくて飲む人もいるし、気を引きたくて飲む人もいるしね。あとは引きこもりだな。引きこもりの中にどれぐらい統合失調症や自閉症スペクトラムみたいな人がいるのか、そういう人達をこれからどうしていくのか、考えなきゃダメだね」
実際に、街中や家で暴れて強制入院になった患者は、私も多く知っています。ただ、大暴れの背景には、それなりに理解できる事情があることが多く、長期に渡って甚大なストレスやトラウマを抱えてきた人が少なくなりません。こうした真の原因と向き合い、環境調整なども駆使して患者を支えられるのであれば、強制であっても精神科病院に入院する意味はあると思います。ただ、受け入れた強制入院の患者を、多量の薬や隔離、身体拘束でひたすら抑え込むことしか考えない病院が目立ちます。患者は自尊心を削がれ、より深いトラウマを抱えて地域に戻り、福祉の世界に滞留していくのです。このような負の連鎖を防ぐには、精神科医療の質の向上が欠かせません。
NHKの番組では、新型コロナに感染した患者を大部屋に閉じ込めて、真ん中に簡易トイレを置いて放置するなど、劣悪な対応をした病院(X病院とY病院)も登場しました。日精協として、なんらかの処分はしないのでしょうか。
「X病院にしてもY病院にしても知っているけど、あれはひどいよね。神戸の神出病院の時は、日精協として監査に入って指摘事項を伝えようとしたんだけど、退会するってことで、今は抜けている。結局、神出病院は(調査メンバーを)院内に入れさせてくれなかった」
「日精協には、支部長の承認がないと入れないんですよ。各都道府県で、支部長が『あそこはちょっとなあ』という病院が100近くあるんだけど、そういう病院は入ってないんです。加盟してないんだよね。不祥事があった時は必ず監査に入って、問題を指摘しています。茨城のホスピタル坂東もそうだったな。診療報酬の不正請求でね。めちゃくちゃなことをやっててさ。あれも厚労省の役人が指導したんだろ」
「神出病院も、事情を聞かせてくれと言ったけど、『コロナで、コロナで』と言われて。でも、話を聞いてこないとダメだってなって行ったんだけど、入って来られると困るからうちは退会します、となった。退会されたら、我々は入る権利も何もないし」
★「X病院とY病院は、最近までどこの病院か分からなかったから、(監査は)まだですね」(2021年8月19日時点)
「両方とも会員病院でしたよ。XとY。ただ、あそこは日精協の会合には出てこない。東京は会員病院が60くらいあって、40くらいでコロナが出たんだよ。3分の2だね。病院によっては、(XやYのように)畳部屋の方が落下しないからいいって言うけど、ただ点滴する時が大変だよね。色んな病院があるから、ひとまとめに精神科はって言われると困るんですよ。みんな一生懸命やっているんだけどね。ただ、オーナー権がないようなところはね。精神科病院で何かあると、ほらまた精神科病院で起きたと。どの集団でも、変なことをやるやつはやるからね」
日精協は9月15日、会員病院(1185病院)を対象とした「新型コロナウイルス感染症対応状況及びワクチン接種状況に関する調査」(8月23日時点)の結果を発表しました。回答した711病院のうち、44%にあたる310病院で感染が発生し、総感染者数は5091人(患者3602人、職員1489人)に上りました。「転院要請したが転院できずに死亡」の患者も235人に達しました。感染症対策でも、精神科病院は厳しい状況にあります。
「精神科病院はもともと閉鎖空間だから。病棟の中にアルコールだとか、消毒剤も置いておけないんだよ。飲んじゃうから」
★「食事の時に、ナース達が手にかけてあげるとかそういうことはできますけども。精神科ではマスクをしてっていうこともできない。それは疾病特性ですよね。他の部屋に行ってはダメですよと言っても、今でも後ろから僕に抱きついてくる患者さんがいますから。NHKの番組では非常に悪いように取り上げられましたけど、レッドゾーンとグリーンゾーンに精神科は分けることができないので、全部レッドゾーンにしてしまったんですよね。あの病院のやり方は、確かに問題ですけどね。日精協としても、感染症に関してはレッドゾーンにして、そこに感染した患者さんをまとめられるようにできませんか、ということを厚労省にお願いはしていたんですが、それはできないと」
「インフルエンザの時に、インフルエンザの患者さんを4人部屋にまとめるよね。そういうことは従来やっているのよ。そうじゃないと病棟全体に広がりますから。しかし、それで(NHKの番組に登場した病院のように)真ん中にトイレを置いて非人道的なことをするから、問題になるんですよね」
「今、コロナにかかると、一般の患者さんでもなかなか入院させてくれないんだから、精神科病院の患者さんはなおのこと難しいね。精神科病院は、自分のところで治療しなきゃいけないってなるよね。呼吸器の先生がいない精神科病院で感染が出た場合に備えて、治療の指導をするようなネットワークを日精協で作らなきゃだめだなと思っています。呼吸器の専門医がいる会員の病院と連携してね。ブロック別に、互助組織みたいなのを作らないとダメだね。そうじゃないと、普通の病院に頼んでも相手にしてくれないと思う。だから感染者病棟も、日精協の会員病院の中で力のあるところが作って、各都道府県に3か所くらい必要だと思っている。感染者病棟として作っておいて、患者が入っていてもいなくても運営費は(公が)払えって、そういうことですよ」
増加する身体拘束については、日精協はどう考えているのでしょうか。聞いてみました。
★「隔離や拘束は、患者さんはされたくないので、医療者も基本的にしたくないんですよ。それに、隔離拘束したら管理が大変というのもあります。巡回が多くて面倒だし、やりたくないんです」
「隔離は手続きがたくさんあるのに、診療報酬はなんにもついてこないよ。あれだけカルテを書かせるのに、なんで点数がつかないんだって言っているけど」
★「(身体拘束数が近年急増したのは)高齢者が増えているから。(拘束の)指示まで入れてでしょ。精神保険指定医の立場から言うと、指示は出すと思います。もし興奮したら隔離拘束してね、と。なければしないで。夜中に起こった時に、ドクターが各病棟を回って診れるのかっていうと難しいので、予測指示になると思います」
「精神科の身体拘束数が、以前は5000件だったのが10年で1万件になったっていうけど、介護の施設では、1年間に6万人拘束しているんだよ(2015年の厚労省調査)。それがなんで問題にならないで、精神科の1万人の方が問題になるのか。この6万人は、精神保険指定医が拘束の指示を出しているのでもなんでもなくて、誰が指示を出しているのかもわからない。そんな拘束をされている患者さんの人権は、どういう風に担保するんだって。こっちの方が問題だよ。精神科の1万人は精神保険指定医がやっている。でも6万人は、全然無資格のやつがやっているんですよ」
★「(介護の施設では)拘束はやってないってことですよ。そういう概念がないから。(身体)固定ということですよ」
「自分で降りられないようにベッドを柵で囲む。点滴の管を抜かないように手袋をつける。車椅子から立ち上がれないように拘束帯をつける。一般科だと拘束の概念がないので、みんな固定だね」
「精神科の拘束は、仕方なく拘束しているわけであって。拘束をなくそうとしている病院では、外には出てないけど、骨折の手術が倍になったっていうのもあるね。骨折のリスクって、それだけ上がる。拘束しない方が親切なのか、拘束しないで骨折した方が親切なのか、どっちかな。拘束しても部分開放をやっているし、車いすに乗せているし、縛りっぱなしじゃないからね」
★「認知症の老人は、寝るまでの間、30分とか1時間拘束して、あとは解除するというのが多いと思います。寝てしまえば朝までは大丈夫なので」
「部分拘束だよね。終日拘束じゃなくて」
現状では、明らかに過剰な身体拘束が頻発しています。病院は「管理のしやすさ」を優先するのではなく、患者の回復につながる「医療」の提供を優先して欲しいと思います。

患者さんはファミリーだから/長期入院で儲ける気はない
私が以前にスクープした千葉の石郷岡病院事件(民事訴訟で和解成立)や、神戸で昨年発覚した神出病院事件など、精神科病院では医療者による患者虐待が後を絶ちません。神出病院の問題は、病院職員の内部告発で表に出たのではなく、警察が看護職員を別件で逮捕した結果、たまたま発覚しました。精神科病院のような閉じた組織では自浄作用が働きにくく、同様の問題はまだまだ隠れている可能性があります。障害者虐待防止法では、病院職員には、職場で虐待を目撃しても通報する義務がありません。このような虐待事件が続くと、同法の改正を求める声が高まりますが、日精協はどう考えているのでしょうか。
「(法改正については)そのへんはどうなのかなあ。普通は、そういうことがあった場合は、問題の病棟の師長から看護部長に報告が上がり、看護部長が院長と相談して対応していますよ。(神出病院事件では)古手の勘違いしている看護人が変なことをして、それが上に伝わらない体制自体に問題があるよね。それって職員のモラルの問題じゃないのかな。ああいう古手の勘違いした看護人がいるのは、あそこだけじゃないとおもうよ。そういう人たちが変なことをやった時に、上に伝わるようなシステムは必要だよね」
「そうはいっても、全然知らないところでやられて、院長が責任とれって言われてもかなわないね。何かひとつ事件が起こる度に、厚労省は自分たちに被害が及ばないように法改正をやろうとするんだけど、なかなか実現しないことが多いよね。相模原の事件を受けた法改正も進まないでしょ」
日精協は今年、精神科医療安全士という資格を作りました。誰の安全を守るための資格なのでしょうか。
「精神科では、すごく興奮する患者さんもいて、暴力を受ける看護師がかなりいるんですよ。当直体制や日勤の中に、暴力対応をきちんとできる人が入っている方が、患者間の暴力にしても、患者から看護師への暴力にしても、少なくなるだろうと思って作りました。看護師が患者さんに暴力を振るうっていうのは、この資格どうこうではなく論外で、やった時点で懲戒免職ですよ」
★「精神科医をやっていると、患者さんから暴力を受けたことのない人はいないと思います。急性期の患者さんなので、例えやられたとしても殴り返すなんてありえないし。暴力を受けたことがない精神科医やナースはいないけれど、どこにも文句は言えないんですよ」
「だから看護師2人で当直するより、看護師と精神科医療安全士でペアを組んだ方が、そういう時の対応ができるかなと。ひいては看護師の安全の担保にも繋がるからね。(暴力を振るう患者の抑え方などの)トレーニングを受けさせて、暴力に関するプログラムもちゃんと受けさせて、試験をやって協会で認定する。いずれは国家資格にしたいと思っています」
日本の精神科病院では、包括的暴力防止プログラム(CVPPP)を取り入れる施設が増えています。海外の取り組みを参考に開発されたこのプログラム自体は悪くないのですが、その中にある護身術的な要素ばかりが注目されてしまいました。この取り組みを日本で広めるために尽力した大学教員の看護師も「患者をねじ伏せるための技術講習になってしまった」と、私の以前の取材で嘆いていました。精神科医療安全士も、同様の道を歩むのでしょうか。
ですが、患者の暴力に適切に対応できる技能をスタッフが身に着ければ、「暴れたら危ないから」という予防的な発想で行う身体拘束の乱発は抑えられるかもしれません。白黒思考ではない柔軟な考え方が必要です。しかし、何よりも大事なのは、患者を暴れさせない環境を提供することです。病院側が力で攻めてくれば、患者側も力で返す。当たり前です。精神科病院は本来、社会の中で心を疲弊させた人たちが、一時的に心の休息をとる場所なのですから、入院した途端に患者を羽交い絞めにし、隔離、拘束するような野蛮なふるまいは論外です。
精神科病院は、診療の質にも大きな差があります。公立、民間を問わず、医療とは呼び難いほどの質の低いサービスしか提供していない病院もあります。そうした所を避けるためには、各病院の診療実績を知る必要があります。ところが、精神科病院は総じて診療実績の公開に消極的で、患者や家族は受診の参考になる情報をあまり得ることができません。
そこで重要になるのが、国が毎年行っている精神科病院の実態調査(630調査)です。これを見ると、身体拘束数や隔離数までわかります。東京や大阪の市民グループなどは、各自治体への情報公開請求で得たこの情報を独自に集計するなどして、患者や家族に提供してきました。ところが近年、集計方法が変わったことをきっかけに、自治体が630調査の開示を拒むようになり、「日精協が圧力をかけているのでは」との声が上がりました。実際はどうなのでしょうか。
★「(2019年度以降の630調査は、個人情報が特定されない出し方になったので)都道府県がまた開示するようになったでしょ。今は開示されても問題ないですよ。ただ、それ以前には、マスコミが調査の情報をもとに個人名を特定して、『この人は長く入院されているよね』と言って、病院に話を聞きに来ることがあったので、そういうのはまずいということです」
「今は問題ないよ。ただ、誰がどこの病院にどれだけ入院しているかっていう情報が第三者に出ちゃうのは、家族としてはかなわないから、(以前は)抗議した。630調査って、一般科でもやってるの?やってないよね。なんで精神科だけやってるの。精神科を悪者扱いしているのかな。一般科と精神科は同じにすべきだと思うよ」
一般科の病院は、自ら詳細な診療実績データを公開する時代になっています。患者も家族も、そして国もそれを求めている(医療法に基づく医療機能情報提供制度)からです。身体的な不調に陥った人は、各病院が「医療情報ネット」や自院のホームページ、マスコミ(私が関わっていた読売新聞の「病院の実力」等)などで発信している様々な診療実績を比較して、受診先を選ぶことができます。しかし、精神科医療機関はこの部分でも遅れているような気がします。私が精神科病院を対象に「病院の実力」アンケートを行ったときの回答率は惨憺たるものでした。精神疾患はその特性上、診療実績を集計しにくいのはわかるのですが、可能な限りオープンにしようという姿勢が乏しいように感じます。ですが、日精協としては情報提供を積極的にしていく姿勢のようです。
★「(日精協の会員病院も)言われたことは全部出していますよ」
「うちの協会で(630調査の結果や各病院の診療実績を)秘密にするような話でもなんでもないからね」
2019年度以降の630調査のデータは、個人情報が特定されないように集計法が再度見直されました。ところが、今も開示を拒む自治体が少なくありません。神奈川県の消極姿勢は、このWebサイトなどで繰り返し取り上げてきました。また埼玉県は、情報のほとんどを開示したのに、各病院の身体拘束数だけは見られないように、黒塗りにしてきました。こうした自治体の不自然な行動は、強制入院などで精神科病院にお世話になっている立場ゆえに生じた、一方的な忖度なのでしょうか。日精協は、本当に圧力をかけていないのでしょうか。
★「自治体の中には、以前に個人情報をいっぱい出してしまった所があるので、そういう自治体は慎重になっているのかもしれませんね」
「日精協って、何か影の圧力をかけているように思われているよね。政治力を使って悪いことをしているんだ、みたいなね。でも、そんなことはないよ。我々はそんなに偉くないって」
「政治力」といえば、山崎さんは「アベ友」としても知られています。実際、どんな関係なのでしょうか。
「安倍さんは、個人的に大好きだから付き合っているんで。まだヒラの衆議院議員の時、昼食会の講師でよんだの。僕は、その時の彼の話に凄く感銘を受けてね、総理になる器だって思った。それで後援会を作って応援してきた」
「安倍さんのいい所は、国論があったこと。どういう国にしたいか、という目標があったからね。小沢一郎さんともよく話をしたけど、小沢さんは国家観がないんですよ。壊すことだけが目的でね。スクラップはするけど、ビルドの部分がないんだ、あの人には。壊すことにしか喜びを感じていない。だからこの人はだめだと思った」
「安倍さんは総理になってこけたでしょ(2007年、潰瘍性大腸炎の悪化で退任)。あの時、8割ぐらいの支持者が逃げたの。でも僕は、安倍晋三は必ず復活するから、ここは我慢して病気を治せよと彼に言って、応援した。そのことを彼は凄く覚えていて、一番苦しい時にずっとそばにいてくれた人のひとりだということで、彼は僕を評価してくれている。政治献金は、他の先生と同じようにはしているよ。しているけど、そういう話と個人的な信頼関係は全然別の話でさ。安倍晋三に何か頼んだことはないよ。ゴルフをやって、一緒に中華料理を食うぐらいでさ」
★「むしろ、こちらの方がお願いをされていますね。(新型コロナウイルス感染者が多数発生した)ダイアモンドプリンセス号にも、安倍さんから直接、(日精協の医師を)派遣しろと言われて大変でしたよ」
「こっちの方が、貸しがあるよね。あの時も、全員船から降ろせと僕は言ったの。船内で水際作戦なんかやっていたら、必ず船内感染を起こすし、既に起こしていてブレイク寸前になっていたんだから。和光(埼玉県和光市)の税務大学校が1200人くらい入れるんだよ。日本人だけ全部、税務大学校に出せばいいって言ったの。結局、なんにもなんなかった。あの件では、外に言えないような話はたくさんあるよね」
精神科病床数で世界の2割を占める日本。その大部分は、日精協の会員病院に集中しています。この過剰な病床を今後どうするのでしょうか。
「日本の精神科病床の30数万床ってね、マスコミの人達によく言うんだけど、そもそも外国は精神科病床の定義が日本と違うんですよ。EUでは、急性期のみを精神科病床と言っている。日本でいうと、スーパー救急とか急性期治療病棟にあたるわけ。入院基本料の病棟でいうと、10:1とか15:1とか、ここまでの定義が外国でいう精神科病床で、慢性期とかリハビリとかは精神科病床の定義に入っていないんだよ。従って、その定義に基づいて外国は2万床とか3万床と言ってんだけど、日本の30万床のうち25万床くらいは慢性期の病床なんだよ。本来なら、精神科病床って言ってないのにさ。日本ではひっくるめて精神科病床って言うからおかしくなる」
「だから僕は、日精協の会長になって3年間、WHOに行って講演して、おかしいってことを言った。それで最近、WHOは30数万床という数字を出す時に、必ず『日本の定義でいう精神科病床』とくっ付けるようになったよね。でも日本は不勉強だから、相変わらず30数万床が恥ずかしい、みたいな話をしているわけ」
「外国では、隠れ精神病床みたいなのがたくさんあるの。慢性期の。潰れたホテルを買い取って、慢性期の人たちを入れちゃったりしてね。アングロサクソンって、絶対そういうことを言わないよね。日本でいう慢性期の精神科病床に相当するものは、全部隠してある。精神科病床とは言ってない。一般病床という言い方でもないんだよ。アメリカのナーシングホームもそうですよ。ナーシングホームをやっているのは株式会社だから、恥部と呼ばれるくらいとんでもないこともやっているんだよ。そういうことをアメリカのマスコミは絶対書かないよ。医療をやっているけど、ナーシングホームなのよ。だから日本っていうのはすごく真面目なのよね」
「アメリカの精神科病院は、1週間から10日で退院させるんですよ。治っていようがいまいが、保険の関係上、出ないとしょうがないんですよね。あとはみんな外へ、という形になるんですけど。結局、ナーシングホームって私費ですよね。保険が効かなくなっちゃうんで、入れる人はかなり限定されてくる。入れない人はどうするのか。ホームレスになる人も多いと思います。日本では、精神障害をもっている以上は、ホームレスになることは少なくて、保護される形になると思います。制度としては、日本は非常に手厚いですよ」
「(東京都立)松沢病院の以前の院長は、民主党の長妻昭(現在は立憲民主党)と仲が良くて、それで民主党政権の時に、日本の精神病棟を3分の1にするとか言ったんだよね。それならまず、最初にてめえのところでやってみろと思って、『松沢病院がベッド数を半分にしろ』って前に書いたことがある。でも、その後にだいぶ減らしたよね。(前院長の)齋藤(正彦)先生っていうのが、わりとまともでいい先生だったよね」
「診療報酬の仕組みでおかしいのは、人件費というか、スタッフの人数で報酬を決めているじゃない。あれが変なんだよ、だいたい。20代の元気な看護師も、70代の看護師も、頭数だけいればいいっていうわけ。7:1もそうだけど、人の数で医療を計るべきじゃないと思うよ。人数分の担保っていうのもあるのかもしれないけど、きちんとした形での診療報酬のつけ方をするべきよね。何か月で何人退院させたとか、みたいな。ただ精神科病院というのは、治らない患者さんは治らないんだよね。僕も何人か、治らない患者さんを抱えているけどね。まあ、一般科の医療もそうだけど、やぶ医者の方が儲かるっていうかさ」
「結局、精神科は単価が安いから量で勝負しなきゃならないところに問題があるから、精神科の単価をきちんと上げて、病床の稼働率が70%位で経営できるような診療報酬を作るべきだと思うよ。80%を切ったらもう赤字で倒産みたいなね、そんなギチギチでやっているのはおかしい。それともう一つは、さっきも言ったけど、精神科病棟は本来、EUの基準に合ったような形にすべきだと思うんだ」
それでは、WHOの定義でいうところの「精神科病床にあたらない25万床」は、具体的にどうしていくつもりなのでしょうか。
「精神科病床を転換しようという動きの中では、介護医療院にしようという話もあったんですよ。介護医療院は病床じゃないから。介護保険だから。それによって、精神科病床の数を少なくしようと思っていたの。そう思っていたら、介護保険だから市町村長がいい顔しないんだよね。介護保険料に跳ね返るから。それで転換できないんだよ。日精協もそういうことをちゃんと考えて、政策もやっているんだけど、行政の方がそこに乗っかってくれないんですよ」
「相変わらず左の人達が、それは患者の囲い込みだと言うわけだけど、実質的に、精神科病院に入院している患者さんたちのために、街中にグループホームを作れるかっていうと、なかなか作れないんだよ、反対運動で。精神疾患の患者さんたちのグループホームを作るって言ったら、大反対だよ。幼稚園を作ろうとしても反対するんだから。うるさいと言って。現実的な方法としては、病床転換しかないんですよ。病床転換しようと思って、そういう制度を作ると、今度はその制度に乗れないような仕組みになっているの。行政の方がなかなか認めなくて」
「その後の話っていうのはね、今回のコロナで話題になった病床転換と同じ話でね、50床の病棟をグループホームに変えるっていうのは、実際できないと思うよ。病床って6・4平方メートル(患者一人あたりの床面積)で作ってあって、それで4人部屋ですよね。グループホームって個室が前提でしょ。50床の病床を潰したら10人とか15人のグループホームしか作れないんだよ。15人のグループホームを3つ作らなければ50人の患者さんの行き場がなくなっちゃうんだよね。構造上のいろんな問題を考えないで、皆さん簡単に言うんだけど、50人分の収入があったところを15人のグループホームにしたら、そこの経営は成り立たないよね」
「改築の費用も、坪30万から40万はかかるよ。そのお金は誰が出してくれるの。そこらへんはちゃんとして、色んなものがなければだめだよね。一番いいのは、前も厚労省に提案したんだけど、病棟を買い取れと。1平方メートル当たり、いくらという感じで買ってもらって、グループホームを作る時に補助金を出してくれれば、病棟を減らすことが可能だけれども、財政的な援助を全然つけないで何かするっていうのは無理よね。病棟を完全につぶしちゃって、外にグループホームを作るっていうなら作りますよ」
「でもね、国はもう、そんなことする気は全然ないもん。ただ、そういうことをずっと言ってきたので、病棟買い取り制じゃないけど、地域移行機能強化病棟っていう1床あたりの診療報酬を作ってくれた。ただ、それを作るのにも色んな条件を付けられちゃってね、その条件もかなりハードルが高いんですよ。だから僕は、単純に買い取れと言っているんだけど」
「3年以上入院している患者さんだっけな、退院させた場合に、そこの病棟にお金がくっつくんですよ。つくんだけど、1ベッド600万くらいだったね。ただ、今のベッドがある程度満床であることが条件で、95%入っている病院が5%減らして90%にしましたよ、というものにはつくけれども、そこの下のハードルがあってね。85%しか入ってない病院が80%にしても、それはつかない。診療報酬によくあるんだけど、書いてあるけれども取れないっていうパターン」
★「制度がせっかくできても、使い勝手が悪いということなんですね。ガラガラの病院は、それを使えないんですよ」
では、仮に介護医療院に転換できたとして、経営は成り立つのでしょうか。
「精神療養病棟と同じくらいの点数を付けるように僕は働きかけてきたので、経営的にはやっていけるよね。ただ、病床が減ることで騒ぐ先生がいるんだよね。それはそれでしょうがない話でね。患者さんが治った時の受け皿や、慢性期の患者さんの受け皿を作るべきだと、昔から日精協も言っているわけですよ。しかし、国は受け皿を作らなかった。いわゆるナーシングホームも作らなかった。ずっと政策的に病院に閉じ込めていた。そして受け皿を精神科病院に作らせようとする。自分達は作らないでしょ、絶対に」
「病床転換の時も、(元新聞記者の)大学の先生とかが、また日精協が囲い込んでいるとか言うし。囲い込んでいるって言う人たちが、地域にグループホームを作って、我々が作ったんだから出してくださいといえば、出しますよ。でもそういう人達ってさ、言うことは言うのに自分達の手は汚さないんだよ、だいたい。他の分野でもそうだけど、綺麗事を言う人は手を汚さないし、黙っていても行動する人は、黙って行動しているよね」
日本は今後、ますます少子化が進み、統合失調症を中止とした長期入院患者は間違いなく減っていきます。一方、認知症の患者数はしばらく増え続けていきます。この変化をどう見ているのでしょうか。
「新規の患者さんは近年、短期入院になっているし、統合失調症の急性発症とか、その他の精神疾患の急性発症も減ると思うよね。一方では、2040年までは高齢化がずっと進んでいくから、認知症によるBPSD(周辺症状)の患者さんは増えていく。そんな大きな流れがあるんじゃないかな」
精神科病院は、BPSDが強まった認知症患者の受け皿として機能し始めています。そのため「認知症患者を次々と長期入院させて、ベッドを埋めようと企んでいるのでは」といぶかる声もあります。日精協は、認知症患者を食い物にしようとしているのでしょうか。BPSDを改善させたら、速やかに地域に返す本来の役割を果たせるのでしょうか。
「返すよ。精神科に入れると、薬漬けにして縛って、寝たきりにするって言う人がいるけど、とんでもない話で、我々は一般科の尻ぬぐいをしているんですよ。一般科で薬を大量に使われている患者さんが多いので、まず点滴をして薬を全部流しちゃって、それから全部組み立て直すわけですから。入院した次の日、熱発していると思って採血したら、(一般科で多量の薬を使われたせいで)悪性症候群になっているとかさ。そんな尻ぬぐいをさせておいて、精神科の悪口言うもんね」
「うちの病院(群馬県高崎市の山崎会サンピエール病院)は認知症疾患医療センターをやっているから、認知症もたくさん来るよ。新入院の半分くらいの患者さんが認知症だよ。僕は30年ぐらい前から認知症を診ていたから。当時の精神科医は、認知症なんて診なかったんだよ、嫌がって。しょうがないから院長の僕が全部診ていたんだけど。そしたら高齢化して認知症の患者さんがどんどん増えちゃって。すると、認知症を精神科で診るなんてとんでもない、また精神科が新たな儲け口を探している、みたいな叩き方をするやつが出てきたんだよ」
「認知症のBPSDというのは精神科医じゃないと治療できないでしょ。みんな匙を投げて最後に精神科に頼んでくるよ。認知症は、衝動行為や幻覚を持つんだから、基本的には統合失調症などと症状はほとんど一緒だもん。使う薬の量と種類が若干違うけど。一般科では、成人と同じ量の薬をドーンと出すから、先ほど言ったようにデレデレになって、悪性症候群になったりする。老人はすごく微妙な調整が必要なんで、そのあたりを考慮しないからうまくいかないんだと思います」
「一般科では、我々が考えられないような薬の出し方をするんですよ。精神症状で興奮しているんじゃなくて、せん妄状態や意識障害で興奮しているのに、どんどん薬を増やしていくもんだから、余計にせん妄がひどくなって暴れるのよ。3日くらい点滴をやって、薬を流していくとケロっとしちゃって」
「ただ一方では、株式会社を含めて民間の人が認知症のグループホームをばかばか作って、そうしたグループホームは過剰になってきているんだよね。本来だったら、精神科医療が必要なぐらいの人まで入っているよ、グループホームに。やっぱり入院させて、きちんと精神科医療で施設対応ができるまで安定させた状態にして、返してやるっていうのが親切ってもんじゃないかな」
日本の精神科病床は今後、どこまで減るのでしょうか。適正な病床数はどのくらいなのでしょうか。
「今の統合失調症の長期入院の患者さんは、平均年齢が70歳位になっているんですよ。だから、あと10年くらいの間に、長期入院の4万人の患者さんがいなくなるんです。そこで、地域の医療ニーズにあったダウンサイジングをしていかなきゃダメだという話を、日精協の講演で常にしていますよ。単に医療だけじゃなくて、地域の訪問看護とか、グループホームを含めて総括で運営するようなビジネスモデルを新規に提案していこうと思っています」
「(精神科病床は)今の30万床の半分どころか、もっと減るかもしれない。さっき言ったようなEUの基準でいう急性期に特化した形での精神科病床にすると、日精協の会員病院全部を併せて、スーパー救急と急性期治療病棟で2万5000床ですよ、今。これがEUの定義で言うところの精神科病床なの。厚労省はバカだから相変わらず30万床とか言っているけど。自治体病院のベッドもあるから、それを併せても5万床くらいが急性期対応として必要な精神科病床なんじゃないかな。重度慢性期もこれから減るから、20万床くらいの患者さんが不確定要素だよね」
「急性期に特化した病院は、今も効率が良いようになっています。慢性期に特化すると、ベッドの回転率が悪くなるに従って経営状態が悪くなる。日本全国、平均値でやれればいいけど、地域特性があるじゃない。高齢化率が急速な地域と、反対に人口が増える地域もあったりして。地域によって全然違うんだよね。だから精神科病院がこれから進む道は、正解がひとつじゃなくて、5つか6つの正解を作らなきゃダメなの。地域特性に応じたね。協会としては、そこまでは道筋を考えて、あとは各病院が考えること。だって、自分たちが自営でやっているんだからさ」
山崎さんは先ほど、「あと10年くらいの間に、長期入院の4万人の患者さんがいなくなる」と語りましたが、これは聞き流してはいけない部分です。30年、40年と病院に閉じ込められてきた超長期入院患者たちの寿命が病院で尽きるまでに、なんとか地域に戻ってもらうことはできないのでしょうか。
「患者さんを地域に出していくことは、僕はすごく大事だと思っています。でも、現実はそんなにうまくいかない。精神障害は45万人くらいいて、身体障害も45万人くらいいるんだけど、就業率でいうと100対15なんですよ。要するに、精神障害者は地域で就業の場がないんですよ。それで地域でどうやって生活するのってね。住まいの確保も収入がなければできないじゃない。精神障害2級で毎月7万円いかないでしょ。それで地域でアパート借りて生活するって、できるわけないじゃない。そうすると、退院して地域で暮らすこと、イコール、生活保護になるんだよ。だからまず、精神障害者の雇用の部分をきちんとやらなければ、地域での共生なんて夢物語だと言っているんです」
「市営や県営の住宅で空き部屋が出ているでしょ。住居はそういう所を使えばいいんだけどね。民間のアパートは保証人が必要で、そうすると借りられないんですよ。有料で保証人になります、なんていう変な会社があって、そういうところを使わないと地域に出られない」
「美しい文章ばっかり書いている厚労省とは違って、我々は患者さんを直接診ているわけだから、無責任なことはできないんですよ。だから今の状況では、せめてグループホームに行って、デイサービスに通って、くらいのことしかなくて。段々とパートにつなげていくとかしても、1人でアパートを借りて生活するには、最低でも12万はないとできないでしょ。難しいですよ」
誤った隔離収容政策を改めず、超長期入院を放置し続けた国の不作為を追及する精神医療国家賠償請求訴訟(原告・伊藤時男さん)が、昨年から東京地裁で続いていますが、これについてはどうみているのでしょうか。
「抗精神病薬ができる前は、電気ショックやロボトミーしかなかったから、世界的にも精神科病院に長く入院させるようなことが行われていたよね。ただ、薬が出来てからのあまりにも長期の入院は、病院の問題があるな。社会復帰のチャンスを逃したよね。ただ、退院させられるだけの社会的な基盤がなかったのかもしれないし、(伊藤さんのケースは)詳しくはわからないけれど、これからそういうことが起こらないようにするにはどうしたらいいか、過去の反省点も含めてちゃんとしていかなければだめだと思うね」
「ただね、何十年も入院していた患者さんが地域に出ることは、その患者さんの幸せに必ずつながると思う?場合によっては、余計なお世話だと思うよ。病院の仲間たちと毎日会話して、一緒に晩御飯を食べる生活と、見知らぬ地域のアパートで孤独にコンビニ弁当を食べる生活と、どっちが幸せだと思う?地域=善みたいなことをみんな言うわけだけど、長期入院の人がぽっと地域に放り出されても、幸せじゃないと思うよ。それよりは、病院のみんなと冗談を言ってさ、晩飯を食べて、『おやすみ』と言って寝る方が幸せな気がするけどね。僕ならそっちの方がいいな」
「地域に出ろ、出ろといった人が、毎晩家に来てくれるのかと言えば、そんな親切はやらないじゃん。自分の価値観を相手に押し付けて、それでまた『今日もいいことやったな』で終わっちゃうんだよ、そういう人は。その後がないんだもん。そしたら、可哀そうなのは放り出された患者さんですよ。だから4万人は、いろんな事情があって長期入院になっている人たちなのでね。地域に出て幸せな患者さんもいるけど、全員地域で、という話は、ある種のファッショだよね。孤独な方がつらいよ。それでまた精神症状が再発してしまうかもしれないし」
精神科病院の経営者が上記のような発言をすると、角が立つばかりですが、「何でもかんでも地域に」が正解でないことは、その通りです。ただ、数十年ぶりの地域生活に恐怖を抱いていた人でも、実際に生活を始めると「病院よりずっと快適」と心変わりする例が目立つことも確かです。ポイントは、地域の支えがあるかどうかです。出すだけ出して孤立させるような支援は、山崎さんが言うように無責任です。
加えて、病院と地域とをつなぐ懸け橋を、もっとたくさん作っていく必要があるのではないでしょうか。KPの関連組織として誕生し、感性豊かな患者たちの潜在能力を演劇活動や音楽活動などで伸ばす支援組織「OUTBACK」では、民間精神科病院とも連携しながら、芸術文化活動による懸け橋づくりを始めています。
最後に、山崎さんは精神疾患の患者をどのようにみているのか、尋ねてみました。
「孤立に追い込まれた人が多いですね。昔の1級障害の患者さんは年金を多くもらっていたから、うちの病院にも預金を500万円以上も残して亡くなった人がいましたね。それで、家族に亡くなったことを連絡すると、『病院で全部やってください』と言っていたのに、預金額を伝えると豹変して、すぐに飛んで来る。そんなのばかりですよ。精神科の患者さんの中には、そんな境遇で一生を終わる人がいるんだよ。そういうのを見ていると、やっぱり精神障害者に生まれたっていうのは、大変なことなんだと思う」
「精神疾患の人って、自ら好き勝手なことをやって心身を悪くした人とは違って、貧乏くじを引いた人生じゃない。だから、それをどこかで誰かがフォローしてあげなければしょうがないと思って、病院はやっているんだけど。そうやっているのに、なんか精神科病院って精神障害者を食いぶちにして、甘い汁を吸っているみたいなことを言われると、本当に腹が立つ」
「僕なんかおやじがずっと精神科医をやっていたから、小学校の頃から病棟に入って患者さんと遊んでいた。だから精神障害者といっても、全然ふつうの感覚なんだよね。医者をもう50数年やって、80歳になったけどさ、基本的なスタンスは変わらないもんね。昭和41年に医師国家試験を通った時に、一番喜んでくれたのは患者さんでしたよ。そういう気持ちで患者さんをみているからね、患者さんを食いぶちにしているとか、甘い汁を吸っているとか、そういう悪口を言われると癪に障るよね」
「僕の中では、患者さんはファミリーなんだよ。僕を含めて2代目の院長って、みんなそういう感覚だよ。だから患者さんのいろんなことが気になるわけ。入院料は確かにもらっているけど、考え方はファミリーですよ。患者さんと一緒に育ってきたんだから。長期入院で儲けようなんて考えてないよ」